皮皮学,免费搜题
登录
搜题
【简答题】

 空腹なのと寒いのと、それからどうも自分たちのしたことがあまりいいことでもなかったようだということがようやくわかってきたのか、帰りの道は珍しくさんにんとも神妙に黙りこみがちであった。 二郎君の家の前にきたとき、私は思い切って「この芋は全部うちで買いますからそちらは桔構ですよ。ただしあれだけの量はちょっと食べきれませんのでお芋の方は半分ぐらいは食べてくれませんか。」と言った。 「そんな...」 と、二郎君の母親は娘のように眼を丸くして言った。 「いやいいです。」 「でもそんなことはできません。やっぱりこれは...」 「いや本当にいいです。とにかく今度のことはこちらの気の済むようにさせください。それに今日はもうおそいから...子供たちもおなかがへってますし...」私は必死になって私の提案を押し通した。母子家庭の、おそらくきっともう何年も続いているのだろうそのつつましい生活に対してすこしでも力になれれば、という気負いが私のなかにあった。 その夜おそく帰ってきた妻に私はまたこの事件の一部始終を報告した。「門灯の下にいもの小山があるので不思議に思って入ってきたのだけれどやっぱりそういうことだったのか」と妻は私が思ったほど驚かずにそう言った。 「それで買い取っていくらだったの」 「二万八千円」 「わあ、薩摩芋ばっかり二万八千円か...」 と、つまは自分の鼻のあたまのあたりをごしごしとこすりながらなんだかまたちょっと面白くてしかたがない、といったような顔で言った。 「それで二郎君のとこはまあいろいろと大変だろうからとりあえず金はうちが全部出すということにしといたよ。」
空腹なのと寒いのと、それからどうも自分たちのしたことがあまりいいことでもなかったようだということがようやくわかってきたのか、帰りの道は珍しくさんにんとも神妙に黙りこみがちであった。 二郎君の家の前にきたとき、私は思い切って「この芋は全部うちで買いますからそちらは桔構ですよ。ただしあれだけの量はちょっと食べきれませんのでお芋の方は半分ぐらいは食べてくれませんか。」と言った。 「そんな...」 と、二郎君の母親は娘のように眼を丸くして言った。 「いやいいです。」 「でもそんなことはできません。やっぱりこれは...」 「いや本当にいいです。とにかく今度のことはこちらの気の済むようにさせください。それに今日はもうおそいから...子供たちもおなかがへってますし...」私は必死になって私の提案を押し通した。母子家庭の、おそらくきっともう何年も続いているのだろうそのつつましい生活に対してすこしでも力になれれば、という気負いが私のなかにあった。 その夜おそく帰ってきた妻に私はまたこの事件の一部始終を報告した。「門灯の下にいもの小山があるので不思議に思って入ってきたのだけれどやっぱりそういうことだったのか」と妻は私が思ったほど驚かずにそう言った。 「それで買い取っていくらだったの」 「二万八千円」 「わあ、薩摩芋ばっかり二万八千円か...」 と、つまは自分の鼻のあたまのあたりをごしごしとこすりながらなんだかまたちょっと面白くてしかたがない、といったような顔で言った。 「それで二郎君のとこはまあいろいろと大変だろうからとりあえず金はうちが全部出すということにしといたよ。」
拍照语音搜题,微信中搜索"皮皮学"使用
参考答案:


参考解析:


知识点:




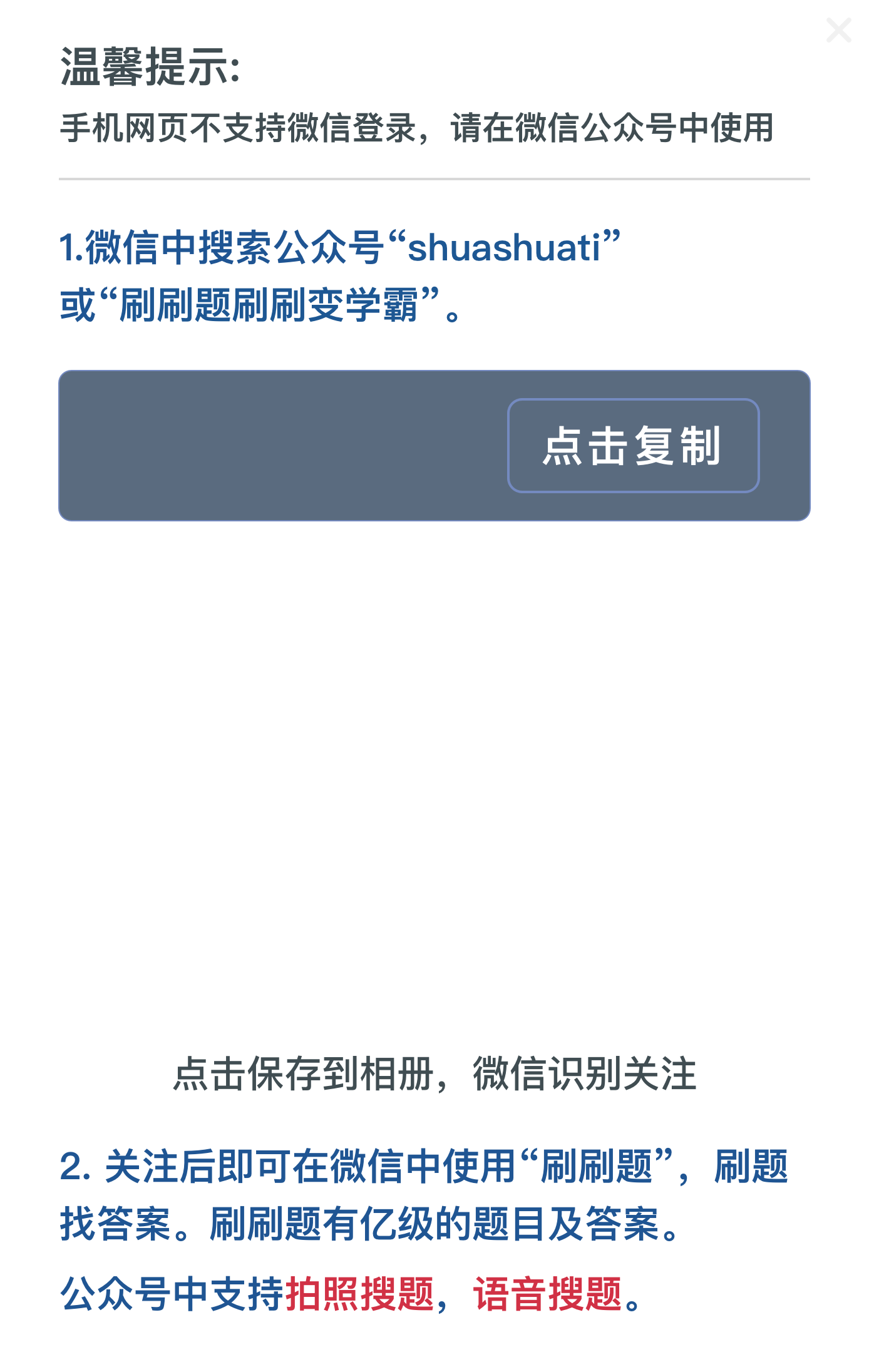

皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【简答题】新闻背景材料的类型主要有哪些?
【单选题】关于细菌的细胞壁结构与组成,以下哪项不正确
A.
青霉素对革兰阴性菌有明显的抗菌作用
B.
青霉素对革兰阳性菌有明显的抗菌作用
C.
革兰阴性菌细胞壁中的脂多糖是细菌内毒素
D.
革兰阳性菌细胞壁的主要成分是肽聚糖
【简答题】新型模具材料的种类有哪些?
【单选题】关于细菌的细胞壁结构与组成,以下哪项不正确
A.
革兰阳性菌细胞壁的主要成分是肽聚糖
B.
革兰阴性菌细胞壁中的脂多糖是细菌内毒素
C.
青霉素对革兰阳性菌有明显的抗菌作用
D.
青霉素对革兰阴性菌有明显的抗菌作用